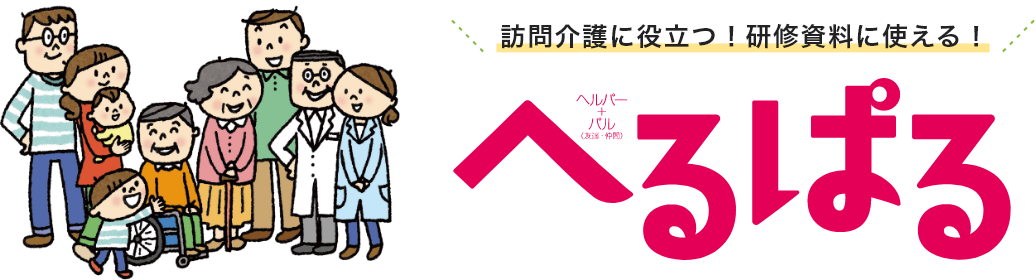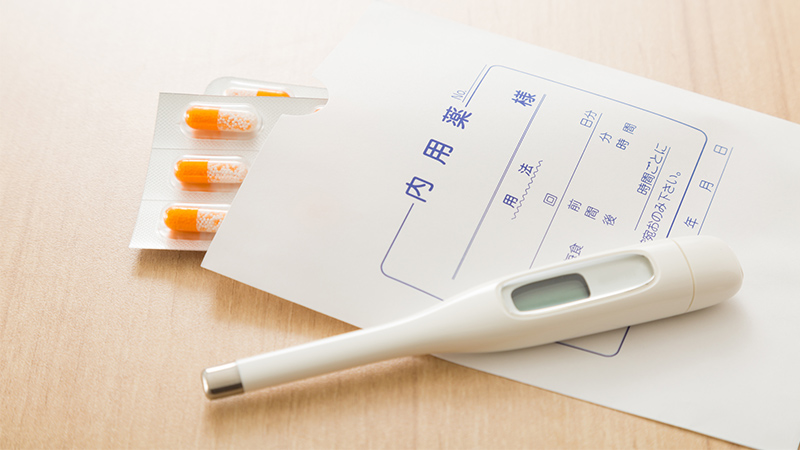“医療行為ではない”とされる行為の対応と「これは医療行為?」と迷うケースを考えよう
訪問介護職は医療行為をできないことはいうまでもありませんが、平成17年に出された通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」で、“医療行為ではない”とされるものが明記されています。ですから、その内容をしっかり認識しておく必要はあります。
この通知を要約すると、一部条件付きのものも含め、左記は“医療行為ではない”と考えられます。では、訪問介護職は一部の条件を満たせばこれらの行為を行うことができるのでしょうか?
解釈としては問題ありませんが、それはあくまでも法律上のことで、実施するうえでの技術や問題が起きたときの責任が免除されるわけではありません。特段の研修なども設けられていません。そのような状況から、内容にもよりますが、これらの行為は積極的に認められたものではないと解釈するほうが妥当です。
つまり、訪問介護計画にあらかじめ「座薬や浣腸の介助」などを位置付けることは推奨できません。実際の現場で想定されることとしては、
●訪問したら高熱があり、主治医や訪問看護師に電話で相談したところ、頓服で座薬が処方されているので使用してほしい、という指示が。対応できる家族がおらず、訪問看護師もすぐの訪問が難しい場合、ホームヘルパーはサービス提供責任者などに確認を取ったうえで、緊急対応として行う
といった場面が挙げられます。ただし、座薬挿入が未経験のホームヘルパーであれば避けるべきです。

一方で、体温や血圧測定などは入浴介助時に行うことが日常的ですし、服薬介助や口腔ケアなどはむしろ重要な内容です。これらの行為は計画に位置付けたうえで、しっかりと技術を修得したうえで、対応するようにしましょう。
ちなみに、平成24年4月から施行された「社会福祉士及び介護福祉士法」改正によって、介護職員にも痰の吸引と経管栄養の介助が認められました。これらは指定研修の受講義務や医療体制の確保などが求められており、ある程度の技術と責任の担保が定められています。そのため、訪問介護でも身体介護で算定が可能になっています。
監修・執筆/能本守康
介護福祉士、主任介護支援専門員、相談支援専門員、日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャー、日本介護支援専門員協会常任理事、(株)ケアファクトリー代表取締役などを務める。著書に『Q&A 訪問介護サービスのグレーゾーン改訂版』(ぎょうせい)などがある。
写真/PIXTA フォトライブラリー