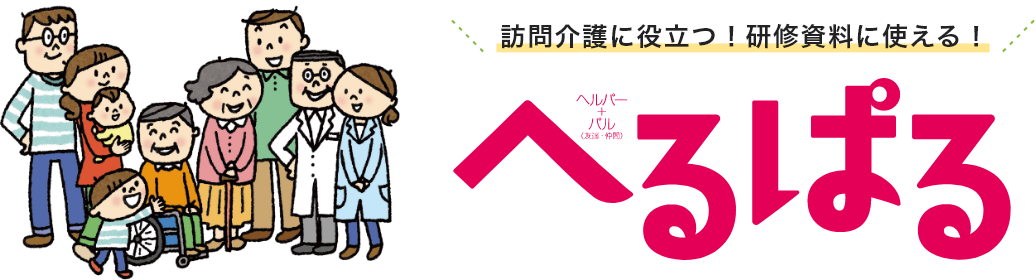生活リハビリテーションを詳しくみていこう!
生活リハビリテーションは、基本的にそれまでのリハビリテーションで獲得した身体機能が維持できるよう、その後も自分で実行するものです。
しかし、できるようになったとはいえ、体の機能的に多少困難なことを自宅&自らの意志で実行するのは容易ではありません。今までは隣に理学療法士などがいて、的確な助言や支援があったのに、自宅では自分ひとりで行う場合もあるでしょう。
となると、「転ぶと怖い」「ほかのところを痛めてしまいそう」など、消極的になる人もいるかもしれません。せっかくできるようになった機能を使わずにいると、また動けなくなってしまうことも想定されます。
ですから、自分で継続して行うよう促してくれる存在が求められるのです。それが訪問介護職であるといえます。
例えば、生活場面での行動を隣で見守りながら「これはできるようになったと理学療法士さんから聞いています。私が見守っていますから、安心してやってみてください」などと声をかけて支援します。これはまさに、訪問介護職の基本的視点でもある「自立支援」といえます。
さらに、今年4月の介護保険制度改正において「生活機能向上連携加算」が強化されました。
これは、訪問介護と医療保険や介護保険でのリハビリテーションを利用している人の場合、理学療法士などのリハビリテーション専門職と訪問介護のサービス提供責任者が連携を図り、リハビリテーション専門職の助言に基づき、自立支援の観点から訪問介護計画を策定して実施した場合に算定できるものです。
まだ算定率が低いといわれていますが、利用者の自立した生活を叶えるためには有効な手段です。利用者の同意のもと、促進を図りたいものです。
監修・執筆/能本守康
介護福祉士、主任介護支援専門員、相談支援専門員、日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャー、日本介護支援専門員協会常任理事、(株)ケアファクトリー代表取締役などを務める。著書に『Q&A 訪問介護サービスのグレーゾーン改訂版』(ぎょうせい)などがある。イラスト/藤原ヒロコ