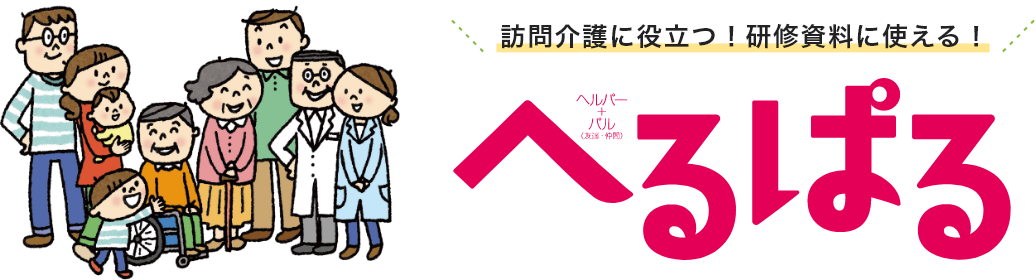運営基準にある「訪問介護の現場での利用者の口腔に関する問題」とは、具体的にはどういったことでしょうか。利用者に起こりうる、おもな口腔の問題とその原因を確認しましょう。
口臭がする
舌苔(ぜったい)(剥がれ落ちた口の粘膜などが舌に溜まって腐敗すること)が口臭のおもな原因。歯周病菌も臭いの原因となる物質を発生させる。
歯や歯ぐきが痛む・出血する
むし歯(歯垢のなかの細菌がつくる酸によって起こる)や歯周病(歯周病菌の増殖によって歯ぐきに炎症が起こる)が原因で歯や歯を支える歯ぐきが痛んだり、出血する。
唇に出血が見られる
唇の乾燥やドライマウス、服用している薬の副作用などにより、口角(唇の端)が切れやすくなり、出血する。
口腔の問題と誤嚥性肺炎
誤嚥性肺炎とは、口腔内の唾液や細菌、食べ物などが誤って、気道に入ってしまうことで起こる肺炎のことです。厚生労働省によると、誤嚥性肺炎を含む肺炎は65歳以上の高齢者のおもな死亡原因の第3位であり、その多くが誤嚥性肺炎によるものです。
『へるぱる2018 11・12月』では他の口腔の問題についても取り上げています。
監修/小玉 剛
公益社団法人日本歯科医師会・常務理事。こだま歯科医院・院長。歯学博士。1985年、こだま歯科医院を開設。東京医科歯科大学歯学部講師、東京医科歯科大学歯学部附属歯科技工士学校講師をはじめ、明治薬科大学客員教授などを歴任後、2016年より公益社団法人日本歯科医師会常務理事に就任。イラスト/佐藤加奈子