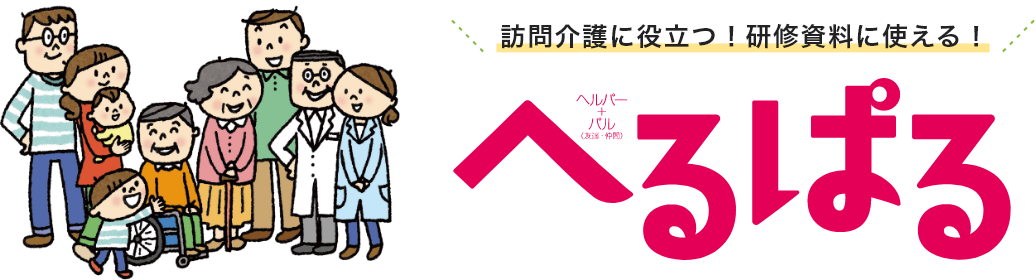ハラスメントを許さない介護現場に変えていく
様々なハラスメントが問題視されていますが、なかでも近年、カスタマーハラスメント(以下カスハラ)が深刻化しています。介護業界も同様で、特に利用者宅でサービスをおこなう訪問介護は他の人の目が届きにくい分、より対策を講じる必要があります。そこで『へるぱる2024 7・8月』では、改めてカスハラ対策を取り上げ、「起こる前」「起こった後」の2方向で考える重要性をお伝えしています。
大事なのは「ハラスメントかどうか」ではない
訪問介護職の皆さんからよく聞かれるのは、「ハラスメントかどうか判断が難しい」という声です。しかし、大事なのは以下の3つの視点で見ること。どれか1つでも該当していたら、スタッフを守るために必ず対応が必要です。
- スタッフが傷ついていないかどうか
- スタッフが安心・安全に働ける環境かどうか
- 利用者や家族等とスタッフの信頼関係が損なわれていないかどうか
本誌では、「起こる前」「起こった後」の対策だけでなく、実際に訪問介護の現場ではどのようなカスハラが起こり、どう対応しているのか実例も紹介しています。ぜひ、お手に取ってご覧ください。
監修・執筆/宮下公美子
社会福祉士、公認心理師、臨床心理士。高齢者介護を中心に、介護現場でのハラスメント、地域づくり、認知症ケア等について取材する介護福祉ライター。できるだけ現場に近づき、現場目線からの情報発信をすることがモットー。取材活動をしつつ、社会福祉士として認知症のある高齢者の成年後見人、公認心理師・臨床心理士として神経内科クリニックの心理士、また、某市の介護保険運営協議会委員も務める。著書に『介護職員を利用者・家族によるハラスメントから守る本』(日本法令)などがある。
イラスト/フジサワミカ